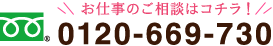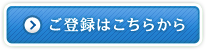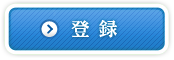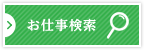アパレル販売員の服代はいくら? ショップ店員の社販事情
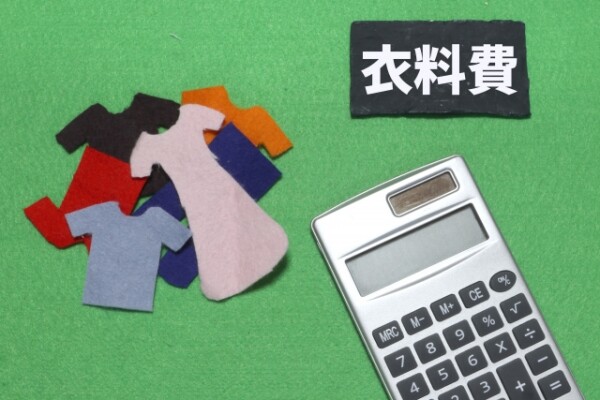
おはようございます♪ウイングです。
みなさんのなかには、「アパレルバイトをしてみたいけど、洋服代ってどのくらいかかるのかな……」と心配している人もいるではないでしょうか。
そこで今回は、アパレル販売員の洋服代についてくわしく解説します。
トレンドファッションをおしゃれに着こなす、ショップ店員の社販事情とは?
アパレル店員は服を買わなくてはいけないの?
ショップスタッフの洋服購入は、義務付けられることはありません。
お店の服を着用したうえで接客するのは、アパレル販売員としての大前提ではありますが、『着用=購入』ということではないのです。
販売している服を着用するにはさまざまなシステムがあり、ここ数年はとくに働くスタッフへの負担が軽減するように配慮されています。
販売商品の購入方法や規定などはメーカーにより異なるため、募集要項や面接時に確認しましょう。
お店の服を買わなくても働ける?
所属するショップやブランドの服は、購入しなくても働くことができます。
配属されて間もない新人スタッフなどは、ブランドの雰囲気に似た私服を着用して店頭に立つケースもめずらしくありません。
そしてある程度の期間が経過すると、メーカーやショップの規約に沿った方法で着用するといった流れになります。
これらの手段や規約もメーカーによりますが、「給料の大半が洋服代で消えてしまう!」といったことはないので安心です。
このあとは、アパレル販売員が商品を購入する方法やシステムについて説明しましょう。
制服
近年では、アパレルショップにおいてもユニフォームを着用するところが増えています。
それは、ブランドイメージを前提に考案されたデザイン、年間を通して着用できるアイテムなどが中心。
また、シャツやブラウスが2パターンほど用意され、ボトムスは好きなものを着用できるなど、その方法もさまざま。
メーカーによってはシーズンごとに制服を用意するなど、ブランドイメージや方向性に合わせて調整しています。
貸与服
貸与服は販売商品や貸与品番アイテムを貸し出す制度。
制服と似たイメージがありますが、制服よりもアイテム数やデザインバリエーションが増えたり、新しい貸与服への切り替えが早いのが特徴となります。
生産枚数が多い打ち出し商品やフェアー対象品番、シーズンのメイン商品など、売り込み商材が貸与服となることもあります。
また、貸与服を前提として生産するケースも。
社販・社割
社販や社割といった用語は耳にしたことがあるかもしれませんが、『社販=社員販売』・『社割=社員割引き』をさします。
これらの制度はアパレルメーカーのほとんどが採用していて、定価の30~70%ほどでの購入が可能です。
処理方法や支払いまでの流れはメーカーによって異なりますが、社販したい商品があったときは、店長に許可を得てから規定に沿った手順で処理を行い、割引き後の金額が翌月の給料から天引きされるといったプロセスになります。
制服手当て
制服手当ては店頭着用商品の購入時に一定の金額が補助される制度で、社販や社割と同様に購入費用の負担軽減を目的としています。
社販や社割との併用の有無、補助金額などもメーカーによりますが、5,000円、10,000円、15,000円など、購入金額に応じて変動したり、購入金額に対しての割合で算出するなど、規約に沿った金額を補助。
もちろん手当てが支給されるのは店頭着用商品を購入した月のみとなり、制服購入がない月は支給されません。
サンプルセール
サンプルセールとは、商品化される前の試作品を低価格で購入できるシステム。
サンプルセールは定価の90%引きほどで購入できるため、アパレル店員にとってもっともうれしい制度といえます。
サンプルは、シルエット、素材感といった全体的なイメージを確認したり、カタログや雑誌掲載に使用する目的で制作されるため、ちょっとしたディテールやデザインなどが実際の商品とは異なる場合もありますが、そのほとんどが店頭着用に支障のない範囲。
スタッフによってはサンプルセールでまとめ買いをして、商品入荷の時期に合わせて店頭着用しています。
私服勤務
メーカーやショップ、取扱いアイテムによっては、私服勤務ができるところもあります。
この場合、取扱い商品やショップのイメージに合わせた服装を前提としたり、雑貨店であれば白Tシャツ×ジーンズなど、着用アイテムを大まかに指定しているケースが多いようです。
また、靴やバッグ売り場、アクセサリーショップなどは、白ブラウス×黒スカート(またはパンツ)というように、指定のアイテムとカラーであれば私服着用が可能に。
アパレル店員ならではのメリットがたくさん
アパレル業界には、社販や社割、サンプルセールなど、販売員だから利用できるシステムがたくさんあります。
これらの制度を活用しつつ、おしゃれも楽しめるのがアパレル販売員の仕事。
アパレルショップで働きたい、アパレルアルバイトをしてみたいと考えている方はぜひ参考にしてくださいね♪
2022/07/20
2022年夏のバーゲンセール~アパレル実店舗の売り上げを上げる方法
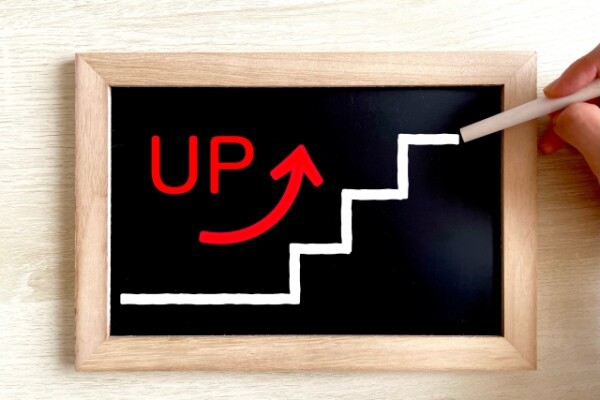
こんにちは!ウイングです(^^)/
アパレルショップで開催される夏のバーゲンセールは、毎年楽しみにしている人も多いイベントのひとつ。
コロナ禍の行動制限が緩和されつつある今年はとくに、アパレル実店舗における売り上げ拡大のチャンス!
そこで今回は、バーゲンセール期間中に売り上げを伸ばす方法や接客販売のコツについても解説していきます。
セール前準備が売り上げを左右します
セール前にはさまざまな準備が必要となり、それらの作業は遅くともスタート日の2週間ほど前から着手するイメージです。
セール対象品番の確認とチェック、セールスタート在庫の予測、プライス変更などが代表的ですが、ほかにもたくさんの作業があります。
セール前準備をスピーディーにこなすのはもちろんですが、大切なのは当日以降の作業効率を踏まえた環境づくり。
これらの取り組みを徹底することで、接客販売に専念できる売り場づくりが実現します。
プロパー(定価)時期との違いを知ろう!
セール期間中は、プロパー時期とは異なる点がたくさんあることを理解しておきましょう。
販売価格や在庫量、来店客数の変動をはじめ、客層やピークタイムなどにも変化が見受けられます。
また、接客体制や商品補充のタイミング、レジ会計フロー、休憩のまわし方も変更するなど、バーゲンセール期間中ならでは業務体制、そして臨機応変な切り替えも必要に。
『売れる商品』を見極める
セール期間中は売れ筋にも変化がみられます。
人気のあるデザインやアイテムは引き続き好調消化となりますが、セール期間中に継続的に売れるのが定番カラーと定番アイテム。
これは客層の変化が一番の要因で、ショップやブランドのターゲットとは異なる客層が増え、売れ筋傾向も変動するためです。
『売りたい商品』の展開方法
売りたい商品とは、在庫量が多い商材や客単価アップが見込める商品をさします。
売りたい商品を売り上げにつなげるには、その商材をいかに魅力的に見せるかがカギ。
では、いくつか具体例をあげましょう。
・売れ筋商品とのコーディネートでトルソー(マネキン)に使用する
・日によって展開場所とコーディネートパターンを変更する
・スタッフが店頭着用で相乗効果をはかる
・スタッフ間でセールストークを共有する
デザイン性が高い場合はシンプルなデザインを組み合わせたり、ベーシックカラーとコーディネートするなど、比較的万人受けしやすいスタイリングを。
レイアウトは見やすくわかりやすく
セール期間中は通常時よりも店頭商品量を増やして展開しますが、レイアウトの見やすさとわかりやすさを忘れてはいけません。
・アイテムやテイストでカテゴライズして展開する
・ニーズが見込めるアイテムは集約して売り上げにつなげる
・デザインやアイテムバリエーションが多い商品は展開サイズを間引きする
・デザインが似ているものは1型に絞る
プロパー時期と同様の内容もありますが、店内が煩雑になりやすいセール期間中はとくに気をつけましょう。
繫忙時はフォーメーション体制で
セール初日や夕方以降などの繫忙時は、接客はフォーメーション体制に切り替えるのがおすすめです。
フォーメーションとは各スタッフの配置を決め、それぞれが担当する場所で専任して接客すること。
対応するアイテム数も限定されるため、同じアイテムを見ているお客さまを並行して接客できるといったメリットがあります。
また、売れ行きや欠品状況も把握できるため、商品の補充漏れも防止できるのです。
繫忙時以外は対面接客を
日ごろから対面販売を実践しているショップはとくに、繫忙時以外はプロパーと同様のていねいな接客を心がけて。
ファーストアプローチ~セカンドアプローチ~ニーズチェック……といった一連のプロセス通りとはいかなくても、明るい笑顔であいさつ、感じのよいお声がけは必須。
状況に応じて聞き出しなども取り入れながら、ニーズに合わせた商品提案を行えるとベスト。
購入せずにほかのショップを見に行かれたとしても、親切ていねいに対応されたお客さまは戻られる確率も高くなります。
価格のお得感もアピール
プロパーとセールでの違いでもっとも大きいのが、価格。
お客さまももちろん、お買い得な商品を求めて来店される割合が高くなります。
タグやプライスを見ている方には、「そちらは〇%オフになります」・「お値引き後は〇〇円になります」など、お得感のアピールも効果的。
また、入店数が少ない時間帯や通勤時間前後、タイムセールにはプライスポップを前面に打ち出すなど、視覚的なアピールもおすすめです。
バーゲンセールで売り上げを挽回!
長期間の行動制限が緩和され、消費者の購買意欲も上昇すると予測できます。
そして、シーズン行事や外出機会が増えるといった季節的な相乗効果も。
商品やサイズも自分の目で確認できる、販売員のコーディネート提案が受けられるなど、実店舗ならではの強みを活かして、売り上げアップにつながる取り組みを積極的に実践しましょう。
2022/07/11